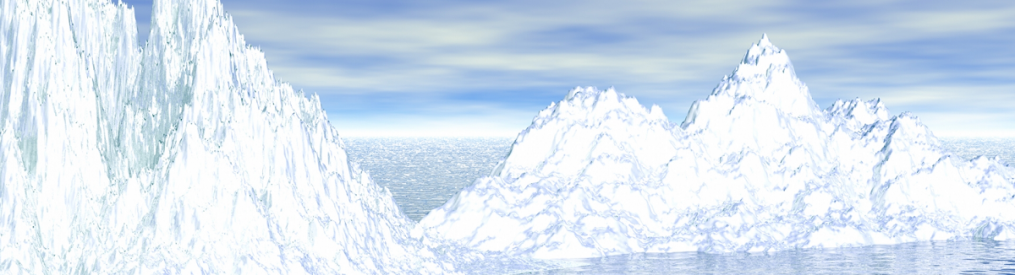今週末出勤なのでまだオンモードですが、1週間がんばったので自分へのごほうびにオメガバです。書いたのは1年以上前だけど。そして全然ごほうびにならない内容だけど。現実逃避という意味でのご褒美なんだ。
氷河って、自分の興味のない相手に対してはすっごい淡泊なのに、一回好きって思っちゃうと結構拗らせるタイプと思います。割り切るのは得意じゃなさそう。
思春期真っただ中の拗らせ男子高校生相手では、いろいろ全体が見えてしまう大人は、同じ土俵で応えてやれないのがつらいところです。
成立しないミロ氷です。全方向に非常に痛いお話となりましたが、了解していただける方は続きをどうぞです。
「やる気がないのか」
「え……?」
「泳ぎに集中できていない。ここのところずっとだ」
「あ……いえ……」
否定したものの、心ここにあらずだったことは確かで、すみません、先生、と氷河はプール底に足をついて瞼に滴る水を手の甲で拭いながら言った。
「タイムも落ちている。この調子では大会に仕上げが間に合わない」
水泳部は月末に大きな大会を控えているのである。
日頃あまり練習に姿を現さない幽霊部員もさすがに顔を出すようになっていて、だから、顧問のカミュも毎日のように授業が終わると同時にやってきて、熱心に指導している。
「すみません、集中します」
そう言って再び泳ぎ始めたものの、グラウンドから響く、野球部の、硬球がバットに当たる音がやけに耳について、ハッと気がついた時には壁に水をかいた腕が当たっていた。
「……っ」
ターンをし損ねてしまったのだ、と気づいて、氷河は立ち上がり、プールの壁で擦ってしまった腕を振って顔を顰める。
「水から上がれ」
ぐい、と腕を取られて振り向けば、水をかきわけ近寄って来たカミュの真剣な瞳があった。
「……あ……でも……」
「今日はもう帰れ。そんな泳ぎでは練習するだけ無駄だ」
「いえ、やります、やらせてください、フラッグを見誤りました。今度はきっと」
「言い訳はいらない。このままでは怪我をするだけだ。帰りなさい」
プールがしんと静まり返る。
カミュは声を荒げたわけではなく、むしろ、低い声は控えめに抑えられていて、離れたところにいる生徒たちには氷河が何を言われているのか聞こえなかったはずだが、だが、凍り付くようなピリピリとした空気が伝わったのだろう。
氷河は言葉なく立ち尽くす。
「無駄な問答でいつまでもレーンを塞いでいられては練習の邪魔だ。この上、他の部員の足まで引っ張るつもりか?帰れ、と言ったのだ、わたしは」
カミュは、日頃の練習を疎かにしているのに大会前だけ顔を出すような、ちゃっかりした部員たちにはたいそう厳しく、冷たく突き放すことも多いのだが、そのカミュをしてそう言わせた、ということは、己はよほど酷いのだろう。
これ以上食い下がっても今日はもう挽回不能だと悟り、氷河は、はい、と項垂れて水から上がる。
のろのろと更衣室へ向かい、タオルを頭に引っ掛け、更衣室に半端に一つだけある樹脂製のベンチへ腰を下ろすと、氷河は憂いを帯びたため息をついた。
まったく何も手につかない。
大好きな水の中にいてさえ、ミロのことばかりが脳裏に浮かぶ。
彼が運命のひとなのかもしれない、という思いは、氷河を雁字搦めに縛り付け、ほかのものを一切寄せ付けなくなっていた。重症、だった。
ほのかに色づき始めていた氷河の恋とも呼べぬ淡いものは、狂おしいほどの劣情と結びついたことで不格好に拗れてしまい、その上さらに、運命、の2文字が加わって、もう、元の形を取り戻せぬほどに縺れ、絡まり、どうにも抜け出し方がわからなくなっていた。
カミュにあんな風に叱られたなら、以前ならしばらく落ち込んでいたものだが、今は、予定外に早く水から上がれたということは、部活終わりのミロと会って話す機会を持てるかもしれない、とそわそわするばかりだ。
水から出ろと叱られて、これ幸いとグラウンドへ向かうなんてあり得ない、とわかっているから躊躇いはしたものの、だが、一度それを思いつくともう駄目だった。
いてもたってもいられなくなって、いそいそと立ち上がって制服に着替え、濡れた髪もそこそこに氷河は更衣室を飛び出してしまう。
グラウンドからノックの音がまだ響いている、と鼓動を速めながら更衣室とプールの間の狭い通路を通り抜けようとして、だがしかし、氷河の行く手は、突然に、ふ、と目の前に落ちた影によって阻まれた。
───カミュだった。
ジャージの上下を纏ったカミュが、長い髪から雫を垂らして、通せんぼをするかのようにプールの壁へ片腕をついて立っていた。
「あ……」
ドクン、と心臓が大きく跳ね、氷河は俯く。カミュと過ごす時間のどれもが楽しくて、もっと一緒にいたい、全部の授業がカミュ先生だといいのに、と、足しげく化学準備室に通ったこともあったというのに、今はとてもではないが後ろめたくてカミュの瞳がまともに見られない。
「少しいいか」
カミュは水の中にいたときと同じ、抑揚のない穏やかな声をしていたが、だが、強く叱責されたかのように、氷河の肩がびくっと跳ねる。
無意識に身体が反応してしまっているのは、叱られる覚えがある表れである。
「わたしと話をしよう、氷河」
声は穏やかなのに、こちらへ、と、硬直してしまった氷河の肩を強引にくるりと反転させたカミュの腕は全くの問答無用で、観念して、氷河は、はい、と項垂れる。
カミュはプールから離れると、氷河を、部室が集まるプレハブ棟を回り込んでテニスコート脇のベンチへと連れて、そこへ腰かけさせた。
ミーティングの日であるのかテニス部員の姿はなく、辺りはすごく静かだが、話だけならほかにいくらでも場所はあるのにどうしてこんなところへ、と、氷河はドキドキしながらカミュを見た。
赤い瞳は氷河ではなく、テニスコートの方角へ向けられている。誰もいないコートの……否、テニスコートのさらに向こう。緑色の防球ネットのそのまた先。グラウンドで、何事かを部員に向かって叫びながらバッターボックスでバットを振り回しているのは……
視線の先にあるものに気づき、あ、と氷河は思わず息をのんだ。
「…………何か悩みでもあるのか」
彼のことで、と、言外に言われた、気が、した。
問いの形をとってはいるが、カミュには氷河の物思いの原因が彼にあることを見抜かれているのだろうか。
だらだらと冷や汗を垂らしながら、氷河は膝に置いた拳を握りしめ、いえ、なにも、と答える。
「近頃、成績も下がっているようだな。化学の提出物もこのところ連続で出ていない。………わたしのところへも来なくなった。何もないはずはない。そうだな、氷河」
カミュが、しばしば欠課する氷河を心配して他教科の課題まで見てくれていたことを思えば、別に何でもないです、などというおざなりな言葉でごまかして逃げるのは不誠実だとわかるのに、でも、なんと言えばいいのかわからない。
俺は実はオメガなのです。運命のアルファをみつけてしまって、他のことが全部手につかなくなってしまったのです、などとは、どうして告白できるだろう。
「他の教科の教員も皆嘆いていた。授業を休みがちなお前はせめて提出物を出さねば、低い評定をつけざるを得なくなる。このままでは単位も危うく、進級をさせてやれるかどうかわからない。それに、もし、進学を考えているなら、今度の大会でそれなりの成績を残しておかねば、特待生が取れる大学の選択肢はぐっと減ってしまう。……それがわからないお前ではないと思ったが」
カミュの言っていることは全く正しい。
こんな愚かしい己を未だ信用し、なんとか立ち直らせようとしてくれている穏やかな声音に、俺はこのひとの信頼を裏切っている、と、胸が締め付けられる。
「……すみ……ません……」
俯いて、俯いた拍子に涙が零れた。
じっとグラウンドへ注がれていたカミュの視線が初めて氷河へ移り、そして氷河の背へカミュの手のひらが触れた。
「お前の人生だ。謝るなら、未来のお前自身に謝れ。社会に出てしまえば、学歴など役に立たぬと感じる場面は多々ある。進学よりほかに大切なものがあると言うのなら、無理にと言うつもりはない。……ただ、学歴はさして役には立たぬが、知識はお前が生きていくのを助けてくれる。学べる環境にあるにもかかわらず、疎かにしていては、生きていく力を自ら手放しているようなものだ。わたしはお前に後悔はしてほしくない」
氷河の性属性を知らないカミュはそういう意味で言ったのではないだろうが、オメガである氷河は、ただでさえ、人生の選択肢が少ないのだ。
就ける職業は限られており、アルファやベータにはさして「役に立たぬ」学歴があってやっとスタートラインに立たせてもらえるかどうかという有様だ。このままずるずると成績を下げていていいことなんか何もない。
カミュの言葉は痛いほどに正論で、ただ、頭で理解しているのと感情が追いつくのは別問題で、乖離した頭と心がすごくつらい。
氷河の背へ乗せられたカミュの手のひらが、やさしい動きで背を撫でる。
「……感情をコントロールすることは難しい。特にお前の年頃では。だから、悪いのは……」
お前だ、ミロ、とカミュが発したのと、じゃり、と靴底が小石を踏んだ音がすぐ目の前でしたのは同時だった。
え、と驚いて顔を上げれば、いつ近づいたのかすぐ目の前にミロが立っていた。
見れば、グラウンドでは野球部がもう片付けにかかっている。
「俺の生徒がどうかしたのか、カミュ」
手にはまだバットを持ったままのミロが二人を見下ろしてそう言うと、カミュは、はあ、と苛立ちを隠さぬ息を吐いた。
「わたしの生徒でもある。……ただの指導だ。授業にも部活にも全く身が入っていない。一体どんな『指導』をしているのか担任教師の顔が見てみたい」
「それで鬼教官は泣くまで叱りつけた?」
ミロの言葉で初めて、己の頬がそれとわかるほど濡れていたことに気づいて、氷河は慌てて拳で両頬を拭う。
ガタン、とまるでベンチを蹴るような勢いで立ち上がったカミュは、切れ長の瞳を鋭くミロに向け、誰が泣かせているのか胸に手を当ててよく考えてみろ、と言った。
「氷河、明日は今日の分も含めてお前のトレーニングは倍だ。いいな?」
厳しい声を残して、そして、カミュは去っていく。
二人取り残されて、しんと静寂が落ちる。
周りに生徒の姿はない。何か話をするなら今だ、と思うのに、声が出ない。これほどの胸の苦しさを表現する言葉を氷河はなにひとつ持っていない。
氷河が黙っていると、ミロが、ふ、と息をついた。
「……下校時刻だ。気をつけて帰れよ」
見れば、数人の教員が、部活終わりの生徒たちの下校指導にと校門に向かおうとしている。
久しぶりに二人きりで話をするチャンスなのに、あなたが俺に言いたいことは、たったそれだけなのか、と氷河の胸が締め付けられる。
また明日な、と、氷河に背を向け歩き出すミロに、氷河は慌てて立ち上がって、待ってください、と叫ぶように言った。
「ミロ、俺、あなたと話したい」
精いっぱいの勇気を振り絞っての言葉に、だが、ミロは、氷河に顔を傾けることなく背中で答えた。
「『先生』、だ。………進路相談ならまた明日に」
「ミロ……」
そんなの、と、氷河は崩れるように再びベンチに尻をついた。ミロはそんな氷河に頓着することなく一度も立ち止まらずに去っていく。
夕陽が彼の意外に柔らかな(だって、もう、その感触を知っている)巻き毛に反射して眩しく、小さくなる背がまたじわりと滲んだ。
**
「珍しいな、ミロ、こんな時間まで残業とは」
人口密度の低くなった職員室、声をかけられて初めてミロは、予定していた時間を大幅に超過して働いてしまったことに気づいた。
「ああ……もうそんな時間か。指導録をまとめていた」
「学期末でもないのに、もうまとめか?えらく気が早いな。切羽詰まっているものでもなし、今日は終わらないか。まだ水曜だ」
そういう彼は執務机の書類をトントンと整理しながら帰り支度を始めている。
ああ、と頷きながら、ミロは職員室を見回した。
ほとんどの職員の姿はもうない。
だが、ここに姿は見えないが、カミュの机のパソコンには電源が入ったままだ。きっと、化学準備室にまだ籠っているのだろう。
彼は残業常連組で、そのくせ出勤時間も早く、おそらく、最も校内にいる時間が長い人間のひとりだ。
生徒のひとりひとりのレベルや弱点に合わせたお手製のプリントを作成するなど、担任クラスを持っていないにしても到底真似できないレベルの緻密な指導ぶりは素直に尊敬していたのだが。
残業の理由は、それだけではなかった、というわけだ。
化学準備室はちょっとしたラボなみに備品が揃っている(塩基配列解析装置や遠心分離機が必要な高校化学があるか?)、と、それは準備室の主をマッドサイエンティストだと揶揄う冗談話として職員室で話題にされることが多かったのだが、全く笑いごとではなく、本当に「教師」の範疇をはるかに越えて研究者紛いのことをしていたとは。
───抑制剤。
アルファの方にも抑える仕組みが必要だ、という発想は、言われてみればそのとおりなのだがカミュに言われるまで思いつきもしなかった。
オメガのヒートが誘発してしまう犯罪も規範の乱れもしばしば社会問題になっているのに、誘惑してしまうオメガの淫蕩さを制御する議論ばかりで、やすやすと誘惑されてしまうアルファの感応性の高さを問題視する議論はミロが知る限りまだ一度もされていない。それも当然だ。社会を作り、動かしているのはアルファだからだ。自分たちの優位性を覆すかのような視点での議論がされるはずがない。
オメガはその絶対数が極度に少なく、彼らの声が世論に反映されることはまずないのだ。
アルファを中心にできている法や社会は、もはや疑問を差し挟む余地もないほど強固に完成している。
オメガへの差別意識はない、と自負するミロでさえ、アルファたる己の性質を抑制しようなどという発想を持ち合わせていなかったのだから、程度の差はあれど、氷河を襲った連中とたいして違わない規範意識で生きてきたのだ、と気づかされた。
もしも、あの時、アルファである己を制御する術があったなら、意図せぬヒートに襲われて傷ついていた氷河に、ごめんなさい、とさらに何度も謝らせるような痛々しい真似はさせないで済んだだろう。
───あの場にいたのが、カミュであったならば。
思考はこのところいつもそこへ巡る。
身体の暴走に精神までも寝食されていた氷河は、狂わんばかりに欲に乱れていて、例えミロが彼のフェロモンにあてられていなかったとしても、あれほど切なく懇願されては拒み通せたかどうかはわからない。
だが、同じ交わることになるなら、選択の余地なく氷河に誘発されて発情した、というよりは、これは己の意志で行動した結果だ、と言えた方が、まだ、互いに救いがあっただろう。
だが、ミロには、見よう見真似で抑制剤を精製するような知識も技術もなければ、副作用のリスクも顧みず自分自身の身体を作り変えんとする自己犠牲精神もない。
カミュと同じことができるかと言えば全くそうではなかった。俺が氷河にしてやれることといったら───
ミロは手元の指導録の束に目を落とす。
左肩の出席番号を眺めながら一枚ずつめくり、10枚ほど捲ったところで指をとめる。
氷河の欠課に課題未提出が増えている。
ミロの授業に至っては、保健室の一件以来、一度も出ていない。
意図しない交わりを持ってしまってしばらくは、複雑な思いをなんとか飲み込み、どうにか日常を取り戻そうと努力している様子が垣間見えていたのに、だ。
あの日以来、プツリと途切れた出席の記録に、ざわざわと心が波立つ。
「よくないな、これは……」
ミロ、話したい、と、切なく呼ばれても、この状態で手を差し伸べても彼のためにはならない、ということを知っている程度にはミロには人生経験も分別もあって、簡単に応えてやるわけにもいかないのだ。
距離を置いているうちに、少しずつ、日常の営みに紛れて、俺のことなど忘れてくれたら、と願っていたが、日に日に思い詰めた様子が増すばかりで、状況が好転する兆しは見えない。
は、と小さなため息を零して、帰宅準備のために立ち上がったときだ。
カラリと職員室の引き戸が開いてカミュが入って来た。
いつの間にか職員室にはもう二人以外の姿は消えている。
人がいたことにカミュは少し驚いたような表情をし、そして遅れて「まだいたのか」と言った。
「お前こそ。……………例の薬か」
ほかに人がいないにも関わらず声を落としてそう問うたミロをカミュは自席へ腰かけながらちらりと見やって、そして、それとわからぬほど微かに頷いた。
「ムウから副作用が引き起こす危険性を聞いたぞ、カミュ。なぜそこまでする。身近に守りたいオメガでもいるのか」
ミロがそうした踏み込んだ問いをするとは思わなかったのだろう。カミュは眉をひそめ、だが、会話を拒絶はせずに、いや、と首を振った。
「言っただろう。これはわたし自身の矜持の問題だ。誰かのためにしているわけではない」
「矜持のために、命を縮める危険を冒していると?」
「そうならないように研究中だ。進んで死に急いでいるわけではない」
それでも、やはり、そこまでするのはミロには理解できない。カミュがそれを矜持の問題だ、と考えるなら、ミロもまた、アルファとして生まれた自分の全てにプライドは持っていて、身体に負担をかけてまでその性質を変えてしまう気にはなれない。
どちらが正しいと言えるものではないが、だが、血塗れの顔で、ごめんなさい、と泣いていた氷河のことを考えれば、酷く苦しい気持ちになってどうにも堪らなくなる。
「ミロ……?」
少しの間、物思いに沈んだミロを怪訝がって呼んだカミュにハッとして、なんでもない、とミロは首を振る。
「……抑制剤を使っていれば相手の性属性は全くわからないのか」
一旦切れたかに見えた会話を、さらに踏み込むミロにカミュは戸惑ったかのようにしばし沈黙し、だが、逃げることもせずに真摯に答えを返す。
「どうかな。同じアルファであれば稀に気がつくことがあるが、その程度だ。少なくともベータとオメガの区別はつかない。あまり意識したことがないから、絶対だと言えるかはわからないが」
「……区別がつかないことで、運命のつがいを逃すかもしれなくともいいのか。アルファとオメガの中には、そうした特別な絆を持つものがあると言うだろう」
あまりしつこく拘っては、ミロが言いたいのは氷河のことであると勘付かれてしまう、と思ったにも関わらず、どうしても問わずにいられなかったその問いに、カミュは目を丸くした。
「運命とはまたずいぶんな……真面目な話か?」
ミロが全く表情を崩さなかったものだから、冗談だと思い笑いかけていたカミュは途中から表情を引き締め、そして、気を取り直すかのようにひとつ咳ばらいをした。
「……まあ、そう、だな。仮に、運命と言うものが存在すると仮定するならば……互いにそうと知らずとも自然に惹かれ合う、そういうものではないだろうか。性属性の区別がつかなければ逃してしまう程度の絆を運命と呼んでは安直に過ぎる。わざわざ他人の性を暴いていい理由になるとは思えない」
全く同感だった。
だが、互いにそうと知らずとも強く相手を感知し合った姿を見た後では、彼の口で語られる「運命」に酷く妬けて、ミロは頷くことができなかった。
───氷河を泣かせているのはやっぱりお前じゃないか、カミュ。
いっそのこと、何もかもここでぶちまけてしまって、彼も、この、苦しく、重いものを背負うべきだ、という思いが込み上げ、だがしかし、それが音となる前にミロは、苦く込み上げたものをそのまま腹の底まで飲み下した。
へんなことを聞いて悪かったな、と言えば、カミュは、自分の方こそいらぬことをしゃべりすぎた、と思ったのか、いや、と気まずそうに視線を逸らした。
そして、話題を変えるかのように不意に渋面となって、「それより、ミロ、昼間のことだが、氷河のことを、お前は、」と続けたのを、ミロは片手で制し、立ち上がる。
「悪いがその件は口を出さないでくれ」
「だが、ミロ、氷河は、」
「カミュ、俺の教え子だ」
鋭く彼の言葉を遮れば、少し言葉を止めたカミュは、みるみるうちに険しい顔となって、「わたしの教え子でもあると言ったはずだが」と言った。
机の上で、きつく握られたカミュの拳が少し震えている。
それが教師としての責任感、なのか、それともそれこそが運命の導く何かなのかミロには知りようがないが、彼が氷河を気にかけていることは確かだ。
ならばもう、心は決まった。
「何を勘ぐっているか知らんが、お前は心配しなくていい。……ちゃんと大会には間に合わせてやるよ」
わたしが心配しているのは大会のことでは、と眉間に大きな皺を寄せたカミュにはもう応えずに、じゃあな、と、ミロは背を翻して、職員室を後にした。
**
ミロの通勤は電車を使ったり、バイクだったり。
その日の気分次第でいろいろだ。
まだ電車が止まるような時間ではなかったが、今夜は無性に走りたい気分で、更衣室でジャージをライダーススーツに着替えた後は校舎裏の職員用バイク置き場へ向かう。
ヘルメットを左手に抱えて校舎を回り込んだミロは、己のバイクの傍に座り込む人影を発見してギクリとした。
「……氷河」
一度は下校したはずだ。門を通る背を確かに見た。
「一体何をしている、こんなところで。生徒がいていい時間じゃない」
「………でも、こうでもしないとあなたと話せないから。連絡先も……わからないし」
進路相談なら明日にと言った、と言いかけ、だがミロは思い直して言葉を飲み込んだ。
数日のうちにははっきりと決着をつけなければならないと心に決めたばかりだ。その決着が少し早まっただけ、と考えるべきだ、ここは。ずるずると先に引き延ばしたいのは、ミロの未練でしかない。
ミロの気持ちの整理のために、まだ十代も半ばの少年を、一度見ただけのバイクを探し当て、日が暮れた後に何時間も待たせてしまうような真似はもうさせてはならなかった。
「……わかった、乗れ」
そう言ってミロは己のヘルメットを少年へと放った。
拒絶されなかったことに安堵したのか、ほっとした様子で慌てて立ち上がり、氷河は促されるままミロの後ろへと跨る。
ミロの腹に両腕を回してしがみつき、背中に全身を預ける健気さに胸が切り裂かれたように痛んで困る。
風を切って学校から遠ざかり、街明かりの中を抜け───
もし、このまま遠くへ連れ去ったなら、と、実行する気もない空想がちらちらと流れ去る景色に浮かんでは消えていく。
氷河はきっと抗うどころか喜んでついてくるだろう。ミロとて、今の立場に絶対の執着があるわけではない。それなりに彼を幸せにする自信はある。
───だがきっと、本当にこれでよかったのか、という迷いはずっとつきまとう。
まだ判断力の未熟な少年の、無限の可能性を閉じてしまったという後味の悪さは長く尾を引き、カミュの姿は常にミロの脳裏をちらついて、いずれ、それが氷河を傷つける。
二人の未来になにも障壁はない、否、どんな障壁も乗り越えてみせる、などと青臭い夢に酔いしれてしまえない大人であることが、今はとても苦しかった。
しばらく目的なく見知らぬ街を流して、ミロは、大きな川沿いの土手でバイクを止めた。
夜遅いこともあって人けはない。
対岸の街明かりで真暗闇というほどではないが、互いの表情がよく見えるというほどでもないのは幸いだった。
「それで?話とはなんだ」
バイクから下りてヘルメットを脱いだ氷河は、まるで責め立てるような口調の、前置きのない性急な問いに少し戸惑ったように視線を狼狽えさせ、わかってるだろ、と言った。
「成績の相談か?進学をどうする気かと皆心配している」
「……俺、『先生』と話がしたいんじゃない」
「ならば相手を間違えたな。俺は教師だ。ほかに君と話せることはない」
ミロ……と、氷河の声が震えた。
「め、迷惑って、ことなのか……?あの……つまり、もう、二人で会うことはないと……?」
「わかりきったことを言わせるのは無粋だな」
でも、あなたはやさしかった、あれは嘘だったのか、と、俯いた氷河の下睫毛で小さな雫が街明かりに光った。
「一夜限りの相手に対する最低限のサービスもわからないとは、とんだ子どもだな。俺ともう一度寝たいなら、せいぜい自分を磨いていい男になってから出直してくれ」
君のヒートに引きずられただけだ、とは例え嘘でも言えなかった。だけ、で説明がつかないほど、気持ちが滲んだ触れ方をしてしまった自覚はあったし、性属性を理由に持ち出したなら、氷河が恢復不能なほどに酷く傷つくことは明らかだった。
こうなっては、つくづく、心を隠しきらなかったのは間違いだった、とミロは己の誤ちを呪う。
今は無理でも、君が大人になればいずれ、と。
言葉にしない約束めいたものを、彼の中に残すことで救われると思っていたが、「大人になればいずれ」が、氷河に予定されている運命ではないのだと知ってしまった今、半端に残した甘い余韻は、浅はかなミロの罪でしかなかった。
「……嘘だ……あなたはそんな人じゃない……」
ここまで冷たくしても氷河は諦めない。少年期の頑なさにミロの方が音を上げてしまいそうだ。
「俺はもともとこういう人間だ。でなければ、生徒があんなアルバイトをしているのを見過ごすわけがない。下心だよ、全部。まんまと悪い男に引っかかって災難だったな」
「やめてください、ミロ……」
俺の好きなひとをそんな風に貶めるのは例えあなた本人でも許せない、と氷河の声が戦慄く。
「……もし、生徒だからだめだというのなら、俺、学校を辞めるから、それなら、」
氷河、と、ミロは唸った。
そこまで思い詰めさせた自分を殴りつけたい。
「だって、学費もないし、前から迷っていた。どうせ学歴があったところで、オメガである俺に就ける職業なんか知れている。ヒートの間つかいものにならなくなる上に、トラブルを持ち込む俺はどこへ行っても厄介者だ。だったら、学校なんて、べつに、」
「は!努力を放棄する言い訳を俺のせいにするのか。ちゃんとした仕事に就いているオメガはいる。君がもし冷遇されるならそれは性属性のせいじゃない、君自身の卑屈さが招いたというだけだ。それでも学校を辞めたいなら好きにすればいい。だが、辞めたところで無駄だ。遊びと本気の区別もつかぬ面倒な坊やなど、俺はごめんだ、会いたくもない」
言ったミロ自身、耐え難い痛みを感じる言葉だ。
みるみるうちに硬直して血の気を失った氷河の耳にどこまで届いたことか。
声なく立ち尽くしている氷河に、ミロは、ふ、と息を吐いて近寄った。
彼が手にしたままだったヘルメットを取って、俯く金色の頭に被せてやる。
「これでもうわかったな。……家まで送ろう。早く帰って課題をしろ。誰かに振り回されるような生き方はするな。自分自身を誇れ。そうすれば、どんな環境でも君の人生は開ける」
少年の純情を弄んだ男の別れの言葉にしてはまともすぎるだろうか、と迷い、だが、導く立場として言わずにはいられなかったその言葉すらも届いていないかのように茫然と俯く少年を、ミロは半ば無理矢理バイクに乗せ、彼のアパートまでの道を走らせる。
ミロの背へすがりつく身体は熱を帯びて小刻みに震えている。声を殺して泣いているのだ、ということは十分に伝わり、最後に触れるその温かさは手放しがたく、ミロは彼にそうとわからぬよう遠回りをして、長く、長く、夜の道を走った。
アパートの前へ辿り着いてエンジンを止めても、氷河はなかなか降りようとしなかった。
彼が納得するだけの長い時間をミロは静かに待って、エンジンがすっかり冷え切った頃に、ようやく観念したか、氷河がゆっくりとミロの背から手を放した。
バイクを降り、のろのろと氷河がヘルメットを外せば、兎のように真っ赤に泣きはらした瞳がその下から現れた。
黙ってヘルメットを受け取ったミロに、氷河は、ず、と、鼻を啜りながら最後に祈るような目を向けた。
「あの日、保健室で……あなたは感じたはずだ、俺たちは運命の……」
「……いや、俺は何も感じなかった」
皮肉なことに、嘘で塗り固められた今日のミロの、それは、唯一の嘘偽りない真実だった。
ミロの瞳に、偽りの色を必死に探している氷河には、だから、何も見つけられなかっただろう。
潤んで充血した瞳はそれでもなおミロを信じるかのように瞬いていたが、やがて最後には、微かに残っていた光を完全に失って、力なく伏せられた。
ミロはそれ以上声をかけることなくバイクに跨り、再びエンジンをかける。
通りへ滑り出して、愛機のバックミラーにちらと視線をやれば、俯いた少年が崩れ落ちるように地面に膝をついたところが小さく見えた。
***
せっかくのオメガバなんだからカノ氷もミロ氷もカミュ氷も気軽にR18いれたいなってとこから始まった話なのに。
気軽……とは……
多分、敗因は学園ものにしたことだ。
わたしはカミュ氷もミロ氷も等しく好きですが、もし、カミュとミロ、全く同じ条件で二人同時によーいドンで氷河を落としにかかったら、ミロ、圧勝だと思うんですよね……。
なんというか、ミロは短距離向きで、カミュ先生は長距離向き?
カミュ先生は卒業まで待てるけど、ミロは待てなくてちょいちょいフライングしちゃう感じ。でも、短期間勝負ならフライングするくらいのスタートダッシュで決してしまう……。
学園ものじゃなければ違う結末もあったと思うけど、ミロ先生が自分で自分を許してくれなかった。
わりと連続でミロ氷書いてきたので、カミュ先生が一歩引いて見守る話が多かったけど、退き際としてはミロの方がシビアな気がします。
カミュ先生の方が氷河の泣きには弱くて絆されちゃう。わりとブレブレ。ミロは日常的に気軽に絆されてくれるのに、いざという時には一歩も退かないんだろうな。
次回のオメガバは、この流れからのカノ氷R18です。ヤケ酒ならぬヤケせっせ的な……
それ終わったらもうストックはないので、オメガバは一旦お休みして、しばらくリーマンをまとめに入る予定です。