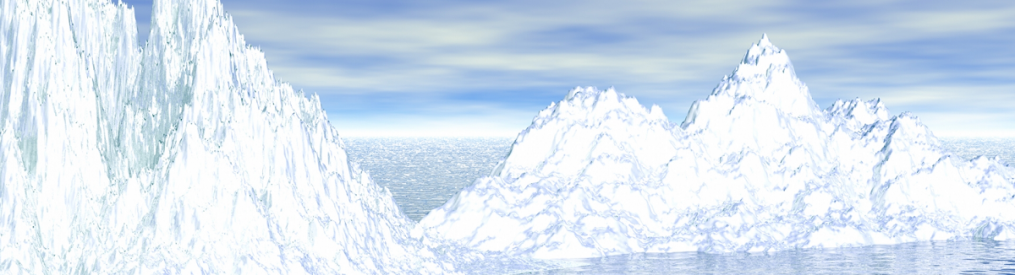勢いで書き始めたけど、だんだん、これ……大丈夫なんかな……って迷走しはじめたゆいまですこんばんは。
冷静になるといろいろ駄目なので、なるべく正気を失っているうちに書ききってしまいたいのですが、ときどき正気に戻ってしまって、あーって頭を掻きむしっています。
だめだ、正気になるな、俺。
とりあえず、今日は、このままカノ氷で終わってもよさそうな流れにも関わらずカノ氷では終われない理由とか。正直、本番よりこっちが書きたかったシーンの方です。ぎりぎりR18はいらないと判断しましたが、まんま、事後です。
途中、カノンがやけ気味に、教師と生徒だったらなんかだめなの??的に開き直っていますが、この世界におけるカノンの価値観であってゆいま個人の価値観ではございませんので笑
もう何度目かしれぬ悲鳴とともに吐精を伴わぬ絶頂を迎えて、氷河はくたりと意識を失ってカノンの腕の中で崩れ落ちた。
氷河の体力がとうとう尽きたのか。
それとも、Ωのヒートは、意識を失うことすら許さぬほど強く激しく身体を苛むというから、気休め程度の抑制剤もようやくいくらか効果を発揮し始めたのかもしれない。
カノンは、まだ欲情の色が濃く残る吐息を吐いて、氷河の身体を抱えなおした。
いったい今は何時なのか。
真昼間に連れ込んだせいで明かりを灯していないバスルームは、廊下のダウンライトが微かに曇り戸を通して漏れる以外は暗闇だった。
明かりなど必要なかった。
手探りで求むそれは、カノンの感覚をいっそうに鋭敏にし、経験したことのない情動にすっかりと我を忘れて、辛がって助けを求めているのか、強請って誘っているのかもうよくわからなくなった、しがみついては喘ぐ身体を貪りつくした。
頼りなく、役立たずの理性を仕方なく取り戻して見つめた空間は、まあ、酷いものだった。
床をぬるつかせるどちらのものともつかぬ体液は既に乾き始めているのもあって、温度と湿度の高い密閉された空間は、むせかえるような精の匂いで淫蕩に茹っている。氷河の制服は汚れ、洗ったところでもうきっと使い物にはならないだろう。
カノンは腕を伸ばしてスイッチを探り、バスタブへ湯を張った。
身体は火照って暑いほどだったため、少しぬるめの湯温として氷河を抱きかかえたまま湯の中へ身体を横たえる。
二人分の体液でべとべとに濡れていた氷河の髪を湯で洗い流してやり、指ですいてやったが、氷河は目を閉じたままだ。
意識を失ったというより、疲れて眠ってしまったのかもしれない。
眠れるほどに人心地を取り戻しているなら、まだ、鈍く燻っているこの淫熱はさすがに堪えねばなるまい。
そういえば、本能が求めるままに幾度も彼の中にぶちまけてしまった、と、思い出し、カノンは氷河の双丘の窄まりに指をやった。
まだ物欲しげにひくひくと蠢く孔に指の腹が触れるだけで、ずん、と重い劣情がカノンの下肢を痺れさせる。
参ったな、と苦笑しながら、カノンはつぷりと指を氷河の中へ埋めた。
熱く収縮を繰り返す襞は、カノンの放った精と彼自身の甘露で濡れている。
かきだす動きで指を曲げれば、湯の中に、どろり、と大量の白いものが広がった。
ん、と鼻にかかる声は甘く、意識なく、カノンに身体を摺り寄せる様には堪らないものがある。意識があろうがなかろうがお構いなしに犯してしまいたくなる。
彼を壊すか自分が壊れるかする前に、と、カノンは氷河を抱いたまま立ち上がった。
ザ、と滴る水雫をそのままに扉を開ける。
氷河を抱きかかえた手でバスタオルだけ取って、雫を滴らせたまま、明かりのない廊下を進み、己の寝室へと向かった。
このままベッドへ氷河を横たわらせればシーツどころかマットレスまで濡れるのはわかっていたが、構わず、カノンはベッドの上へ氷河をそっと下した。
ベッドサイドのダウンライトをつけて、既に半分シーツが吸い取ってしまった雫をもう一度ふき取ってやり、彼が目覚めないことを確認して、カノンは己の髪を同じタオルでわしゃわしゃとかき回す。
少し熱が引いてきたせいか、ひどく喉が渇いていることに今頃になって気がついて、カノンは下だけ穿いて寝室を出た。
明かりをつけずにキッチンまで向かったのは、面倒だったのと、勝手知ったる我が家、その必要性を感じなかったせいだ。
薄暗闇でグラスに水を注いで、ふう、と口元をぬぐったカノンは、明かりのついていないリビングのソファに気配なく座る人影を発見して思わず息を呑んだ。
「…………………戻ったなら戻ったと、」
「言っても気づかぬほど己を失っていたのは一体誰だ」
怒りを感じる段階をとうに過ぎてしまったのか、己と同じ細胞を持つ男の声は酷く静かだ。
「わたしは何度もお前に電話をした」
そういえば、作業着のポケットに突っこんだままにしておいたスマートフォンが、狂ったように鳴っていたかもしれない。言われてようやく思い出せる程度にしか、意識は外の音を拾っていなかった。
「すまん、聞こえなかった。何か用だったか」
とぼけたところでもはや手遅れであろうし、カノンとしては、正直、知られたところでだからどうした、という開き直りもないではなかったが、殊勝な真似をしてみせるのは、ひとえに、兄の心の安寧のためだ。
別々の人間なのだから、そろそろ諦めてくれてもよさそうなものなのに、彼は、しばしば、カノンの行動を我が事のように感じて苦悩してしまうらしいからだ。やってしまったことはなかったことにできないが、せめて、後ろめたさを抱いている様子を演出せねば、この人格者の兄は壊れてしまうだろう。
サガが、まるで舞台俳優のような大仰な仕草で額に手をやって、ため息をつく。
「お前の部屋にいるのは氷河だな」
どうせ、学校から氷河を連れ去ったことは耳に入っているのだろう。
うっすらと事情を察して、慌ててカノンをつかまえようとしたがつかまらず、探し疲れて帰ってきた自宅で愕然とした、そんなところだろうか。
「教師の身で生徒に手を出すとはなんということをしてくれた」
深く眉間に皺を刻んでそう吐きだしたサガの言葉に、く、とカノンは喉で笑う。
「俺は教師などではない。教員免許は剥奪されたからな」
「……あれは不幸な事故だった。わたしは今でもお前に教壇に、」
「兄さん」
既に終わったことを蒸し返されることはまっぴらごめんだったし、小言を垂れるなら、あの抗いがたい強烈な衝動を自分で堪えてみてから言ってくれ、ともカノンは思う。
帰宅して、バスルームで何が行われているかすぐに悟ったに違いないのにその場で踏み込まなかったのは、自身、αである兄にも、Ωのフェロモンに理性を失ってしまわない自信がなかったからではないのか。
同じ細胞を持つ身、カノンが言わんとしたことは、過たず伝わったのか、サガの瞳がそっと逸らされた。
「……………これから、どうするつもりなのだ。まさかあれを番にするのか」
番に、という声に、それとわからぬほど仄かに羨望の色が交じる。
兄にはまだ番はいない。学園の長の立場にいる清廉な兄ですら、その本能には逆らえないのだと思えば、なんだか、人間というものが酷く物悲しくなった。
「俺は前科者だ。(と、言った瞬間にサガは反論したそうな顔をしたがカノンは完全にそれを無視した)αはほかにもいる。わざわざ前科者を番にすることはない。今回のことは事故だ。今後は彼には抑制剤でコントロールさせる」
「……コントロールしきれるのか。学園の教師は皆αばかりだ。厄介なことになる」
厄介、か、とカノンは暗がりで薄く笑った。
「動物」としては発情期を迎えた氷河はもう成体となった。人間が勝手に定めた枠組みに当てはめてみれば厄介事ではあっても、種としては、伴侶を求めてフェロモンをまき散らすのはどこもおかしなことはなく、ごく当然の行動だ。ましてや、Ωは今や希少種だ。種の保存をするために、より強くαを誘因する個体が現れたのは必然ともいえる。絶滅危機に必死に抗う健気な遺伝子を、生徒だから教師だからという理由で、一律に不道徳な行為としてしまうのは、なんだか滑稽ですらある。
生涯を共にしていいと思える運命的な出会いを果たしたなら、情交のひとつやふたつ、何がだめだというのだろう。
サガのように、後から作られた社会規範が常に正しいと思い込む、「立派な」人間たちが、ある種の人間を追い込んでしまうのだ。
Ωという性に翻弄されている氷河と、一度は就いた教職を捨てなければならなかった己はまるで違うようでいて、社会へうまく馴染めない点でどこか少し似ているのかもしれなかった。
とにかく、わたしは対処に戻る、とサガが立ち上がったので、カノンは顔を上げた。
「こんな時間からか」
まだ深夜と言って通る時間だ。
だが、薄闇の中で廊下へ向かって歩き出したサガの横顔に、うっすらと、恥じる色が乗っているのを発見して、カノンはそれ以上引き留めるのを止めた。
たぶん、まだ漂うΩのフェロモンに、理性を揺さぶられているのがサガには辛いのだ。心のうちで何が起こっているのかなど、黙っていればわかりはしないのに、それでも、カノンを責めるからにはそれ以上に己を律しようとする清廉さは、兄らしかった。
黙って兄の背を見送りかけ、だが、唐突に思い出して、カノンは、おい、と呼び止めた。
「学園の教師は皆αなのか?一人の例外もなく?」
サガが足を止めて視線でだけ振り返る。
「…………個人情報だ。答えられない。………なぜ聞く」
「いや、答えられないならいい」
答えずとも、今の態度で確信した。「αばかりだ」と口を滑らせた、それはきっと事実だ。
化学教師の赤い瞳が思い起こされる。
この人格者の兄ですら抗えない本能に、彼は一体どんな魔法をかけているのか、酷く気になった。
*
あまり、よくは眠れなかった。
サガが出て行った後、己の寝室に戻って氷河の隣へ身を横たえてはみたが、ずくずくとおさまらない男の熱が未だ燻り続けていた。
だが、理性を失うほどではない、ということは、恐らく、Ωのフェロモンの支配下からは脱しているのだろう。
通常は一週間はおさまらないはずの発情期がごくごく短い時間で終わったのは、氷河のΩ性は完全には覚醒していないのか。それとも、抑制剤はヒートを起こした後からでも効くのか。真実はわからない。
ともかく、長く人事不省に陥らずに済んだことは、初めての氷河には幸いな結果となったが、あてられて火が付いたカノンは中途半端な熱を持て余すことになってどうにも苦しかった。
氷河は、あどけなさすら滲む寝顔ですうすうと健やかな寝息を立てている。俺をだめにしておいて呑気なものだ、とカノンは苦笑する。
さしこむ朝日に目を眇めながら、カノンはゆるりと身を起こした。
夜のうちにベッドサイドへ運んでおいたミネラルウォーターのペットボトルをあけ、冷たい水を喉へ流し込む。
立ち上がり、抽斗を探って封の開いた煙草の箱をみつけると、片手で掴んでカノンはバルコニーの扉を開けた。
風雨にさらされて少しざらつくサンダルに足を通して、手すりへ身体を預けて、箱から一本取り出した煙草をカノンは唇へと挟む。
ライターを近づけたが、長らく吸わずに放置されていたせいか、しけっていてなかなか火はつかない。顔をしかめながら、三度目に起こした炎がようやく先端をオレンジに輝かせた。
苦み走った煙を胸深くまで吸い込んで、そして、ふーっと長く吐きだす。
ちくちくと指すような刺激が染み渡り、煙を吸い込むごとに、滞留していた熱は、少しずつ、少しずつ、その温度を下げていく。
一本目を吸いきって、二本目をまたすぐに唇に挟む。
決して美味いとは言い難いが、指の先まで痺れさせるような毒々しい刺激は、甘い熱を蹴散らすのにうってつけだった。
三本目へ火をつけたときだ。カノン、と背後から少年の声が響いた。
閉まりきっていなかったバルコニーのガラス戸の向こうで、氷河がベッドの上に身を起こしていた。
身体に巻いてやっていたタオルが垂れ下がり、情交の名残の鬱血痕が残る肌が日に晒されていて、せっかく散らした熱が、またじわりと腰を疼かせる。
唇に煙草を挟んだまま、カノンはガラス戸を開けて室内へ戻った。
彼が目が覚めたときに、なんと言ってやるかは、昨夜のうちにもう決めてあった。
「大人になった気分はどうだ?運動して腹が減っただろう。祝いになんでも食わせてやるぞ」
思い詰めた色をしている氷河の瞳がきょときょとと瞬く。
確認するように、一糸まとわぬ自分の身体を見下ろし、そしてまだ半裸で下しか穿いていないカノンを見つめ、運動……?と戸惑っている。酷く淫らで、かわいそうなほど乱れ狂った時間を、彼は「運動」として即物的に片付けるつもりはなく、例え後付けでも、勘違いでも、何か、心ある行為として意味づけようとしていることは明白だった。
祝いって言われても……、と、俯いた拍子に、さらりと髪が流れ、氷河のうなじがあらわになる。
そこにも残る鬱血痕は、氷河を無我夢中で激しく突き上げながら、噛みたい、噛みつきたい、という衝動を必死に耐えたカノンの理性と本能のせめぎあいの跡だ。
まだ未来に無限の可能性を秘めている彼の番には己はふさわしくない。
にもかかわらず、こうなってしまった以上は、氷河にこれを特別なことだと思わせない必要があった。
自分の性属性を厭うている彼に、恥じるような真似も、後悔するような真似もさせてはならない。
いつか、身体ではなく、心が、誰かを欲しい、と希求する日がくるに違いない彼のために、心ある行為だったと勘違いするような甘い余韻は、微塵も残してはならなかった。
「…………俺……自分ではどうにもならなかった、あんな、あんな……カノンがいなかったらと思うと……」
伏せられた睫毛に、少し、胸は軋む。
「別にΩでなくとも、お前の年で完全に性欲をコントロールできる奴などいない。セックスなんかイカれたもん勝ちだ。ぶっ飛んだおかげで気持ちはよかっただろう?」
カノンはベッドへ腰かけて足を組み、紫煙をくゆらせた。
けほ、と氷河がむせて顔をしかめたが、身勝手で最低な男は、少しも遠慮などしてやらなかった。
気持ちいい通り越して怖かった、カノンは止まってくれないし、と氷河は恨めしそうに上目遣いとなった。止めたら止めたで、ひどいひどいと泣いて強請ったのは誰だ、とカノンは薄く笑う。おかげでちっとも理性は仕事をしなかった。
人の気も知らず、氷河はするりと自分の膝を抱えるように腕を回して、なあ、とカノンへ首を傾けた。
「……それ、俺も吸いたい」
ふ、とカノンは笑う。
そう来たか。思い詰められたりするよりはマシだが、そういう自棄を起こさせたかったわけでもない。
カノンは人差し指と中指で挟んだ煙草の吸い口を己の唇へとあてた。肺深くまで吸い込んでおいて、ベッドの上へ片膝を乗り上げると、氷河の前髪を掴んで上向かせる。
触れた唇は逃げることなくカノンを待っていた。
敏感な粘膜を絡め合わせ、ちゅる、と音がするほど唇を吸う。吐息が甘く変化するぎりぎりのところでするりと離れれば、青い瞳が困惑するように瞬いた。
「……………苦い」
まあな、と、カノンは指に挟んでおいた煙草を唇に戻す。はらはらと、白い灰がシーツの上へ舞い落ちた。空いた手で氷河の髪を一度撫ぜてから離れ、カノンは、氷河へミネラルウォーターのペットボトルを放ってやった。
「スイマーなら煙草はやめておけ。肺をやると泳げなくなる。顧問が煩いのだろう?」
カノンの言葉に氷河は打たれたような顔をし、どこか夢うつつだった淫蕩な空気が、まるで、パチンと弾けたように消えた。
「今、何時だ……!?俺、学校へ行かないと!」
自分がそうなるよう仕向けたくせに、光さす場所へ慌てて戻ろうとする少年の姿は、やはり、少し、惜しかった。
ああ、こんな未練は、全く、俺らしくない。
カノンは首を振って、壁に掛けられた時計を見上げた。
1時限はとうに始まっているが、そのあたりは多分サガがうまく対処しているだろう。
「今なら遅刻で済むが……立てるか?」
聞いた時には、立ち上がろうとしていた氷河はもう、己の腰が砕けていてすっかり使い物にならないことに気づいていたのだろう。少し赤くなりながら、無理だ、と首を振った。
「抑制剤がしっかり効くかもまだわからん。今日のところは休めばいいだろう。……学校に行ったところで数日は水には入れんぞ」
カノンの視線の先に、いくつもの鬱血痕があることに気づいて、氷河は、ああ、と頭を抱える。
それに、制服をだめにしたのだった。新しい制服の調達をサガに頼むのは憂鬱だ、とカノンも頭を抱えながら立ち上がる。
「慌てても仕方ない。まず飯だ。何が食いたい?」
「あー……じゃあ、肉、肉がいい」
「元気だな。朝からか」
「だめなら聞くなよ」
「いや……お前のぶんだけ焼いてやろう。俺はさすがに無理だ」
それってもうおじさんじゃないか、と氷河はくすくすと笑った。
そのとおりだ、と抽斗からスウェットの上を探して頭からかぶるカノンに、笑いの消えた、少しだけ気まずげな声が投げられる。
「ありがとう。カノンがいてよかった。…………抑制剤、もしもだめだったら、あの……」
「大丈夫、抑制剤は効く」
飲み忘れるなよ、とカノンは氷河の髪をもう一度撫でた。
澄んで己を移す、透明な青はとても見る勇気がなかった。
【カノ氷フォローのための解説】
以上でカノ氷ターンは終わりなのですが、これで終わってはあんまりなので、ちょっとフォローしておきます。
うっすら初恋らしき感情をカミュ先生に抱いて、そしてそれをきっかけに発情期迎えてしまった氷河だけど、自分の危機を助けてもらったことで、ぐーっとカノンに気持ちは傾くんですね。だってやっぱり初めてってなんとなく特別じゃないですか。そうか、俺はカノンとってドキドキして、うん、嫌じゃないって確認して、よし、だったら、俺も男だ、腹をくくって責任(?)を取ろう。カノンに番を正式に申し込もう。そんな感じで、氷河は氷河なりに精いっぱい考えていたのです。なのに、カノンがすごくつれない。氷河はもう、生涯の伴侶がカノンでもいいかも、っていうところまで腹をくくったのに、カノンはなんだか言外に「俺はいろいろ経験している」「お前は別に特別ではない」って匂わせてきて、その上、少しよそよそしくて、だから、氷河は、ああ、カノンにはこんなことはよくあることなんだ、俺は勘違いしてはいけないんだ、って何も言えなくなる。氷河だって男の子、一応プライドはあるわけで。カノンが遊びだって顔をするから(そういえばめちゃくちゃ手馴れていた)、まあ、俺もこんなのたいしたことじゃないし、みたいに強がって、その結果の、「俺も吸いたい」なのです。で、そのタイミングで、カミュの存在を思い出させるようなことをカノンが言うものだからそれがダメ押しになってしまって、恋が始まる前に、終わってしまった、そんな感じです。28歳カノンの、この恋愛上級者感よ……初心者氷河では太刀打ちできなくてもしかたない。
一方のカノンは、氷河をどう思っているかというと、やぶさかではないほどに何となく相性も良かったわけで、拒む理由は氷河には全く見当たらない。かわいいし健気だし。でも、だから、それだけに、自分の過去は気になるわけで。事情はどうあれ、前科があるのはもうどうあっても消せない事実。氷河を少しはいとおしいな、と思うからこそ、カノンは氷河には関わろうとはしない。
だから、がっつり激しく致しておきながら、始まれない、すれ違いカノ氷、なのでした。このまま、カノ氷でくっつく世界線も当然あってよいと思います!
カノンの過去は話せばとっても長くなるので割愛しますが、一言で言うなら、生徒の罪をかばった冤罪です。でも、生徒に罪を犯させた遠因はカノンがやんちゃしていた時代にあるので、カノンは真実、己の罪だと思って甘んじて受け入れているのです。そういう過去があるから、罪を犯した生徒ほっといて自分だけ氷河と呑気に幸せにはなれないカノンなのでした。そういう少し屈折したカノンを過去ごと全部まるごと受け止めるぜ、という旦那感を出すには高校生の氷河では経験値が足らないかな、残念だけど。(師と兄弟子と次々死に別れる過酷な聖闘士ならいける!!)
あ、そして、補足。
抑制剤は別に効いたわけではないと思います。自分で書いといてそのへんの設定あやふやだけども。
初めてなので、まだ完全に成熟しきってはいなくて、だから通常よりずっと短めの発情期で終わったのか、あるいは、カノンがえげつなさすぎて、このへんでやめてもらえないともう死ぬ!!と身体が判断したのか笑
そのへんの設定はふわっと、適当でお送りしておりますのでー。
あとあと補足2。
あの、あの、これ、サガ乱入バージョンみたくありません??
わたしはみたい!
わたしだけかな……まあいいか。
とりあえず、ぜーんぶ放出したあとで、気が向いたらいつか書こーって思いました。初心者氷河に何させとんねんって話ですけど、まあいいじゃない、オメガバだから。(免罪符みたいに言うな)
次はちょっと時間が飛んでミロ先生のターンになります。ミロ先生がまた書いてて楽しいんだ……。ミロ氷の息抜きに書き始めたオメガバなのに、やっぱりミロ氷書いて楽しいという……ハア、すき。