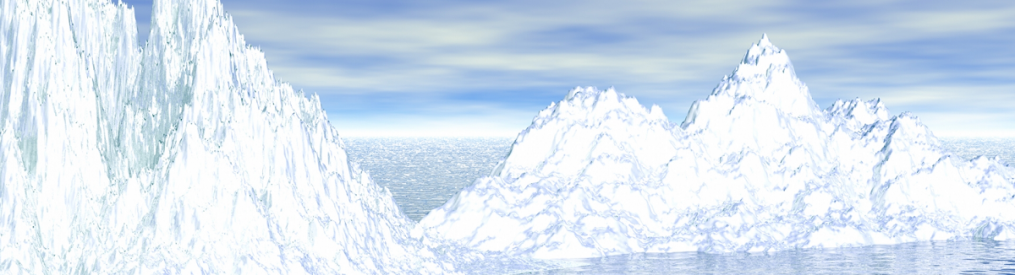ご無沙汰でした、と手癖で書き始めたものの、あんまりご無沙汰な感覚はないなーと思って更新日見たら2ヶ月たってたのでやっぱりご無沙汰でした。時間がたつのが早いのは年齢的なアレと言うかアワワ
ミロ氷編、行きつ戻りつ書いたり消したりしているので、残りはまとめてのUPにしようと思っているので次回更新もやはりご無沙汰でしたから始まってしまいそうです。
UPする文章の倍、もしかしたらもう少したくさん書いて、そこから推敲の過程で消したり足したり順序を変えたりしているわけですが、書いたものの入れる場所がなくなってしまうエピソードも多々あるわけで。
今日はそういう日の目を見ない文章をリサイクル。
ミロと氷河が会話してるだけのエピソードです。
唐突に始まり唐突に終わる。
***
「君は女神をどう思う?」
「……えっ?沙織お嬢さん……?」
ミロが水を向けた話題に、氷河は、突然の方向転換に困惑したように首を傾げた。
「どうって……別に……あんまり俺は好きではなかった」
過去形であることがかろうじて救いではあるが、あまりに飾らなさすぎる感想にミロは苦笑する。
「では、なぜ、その、好きではなかった女神のために戦った」
「なぜって……死にそうになっているお嬢さんを放っておくわけにいかないだろう、人として。それに、まがりなりにも彼女は女神だ」
まがりなりにも、ときた。さすがに苦笑では済ませられずに、少年の不遜を咎める視線をやれば、彼は気まずそうに視線を狼狽えさせた。
「俺はずっと考えていた。なぜ君たち青銅聖闘士が十二宮の戦いでも海底での戦いでも、神をも凌駕するほどの奇跡を見せることができたのか、とな。案外、君のそういうところが答えだったのかもしれん」
「……………沙織お嬢さんを苦手なところが?」
好きじゃない、から少しオブラートに包んでみたのは、氷河なりに気をつかったつもりか。それでもまだいただけないが。
「女神を人間の名で呼ぶところだよ、氷河。君たちはみんな女神を『沙織さん』と呼ぶだろう」
「…………最近では『女神』と呼んでいる」
「だが意識しないと、うっかり人間の名に戻る」
「それは星矢だ。俺は気をつけている」
「まあ聞け。別にそれが悪いことだとは言っていない。俺たち黄金と君たちとではそこが決定的に違う。俺たちには女神は女神だ。『沙織さん』でもなければ、『お嬢さん』でもない。聖闘士としての使命感はあるが、女神を護ることに、君のように『人として放っておけない』という感覚はあまりない」
「でも、女神のために戦っているのは同じだ。呼び名ぐらい、『決定的に違う』ほどの問題ではないと思うが」
うーん、そうだな、たとえば、とミロは少し考え込んだ。
少年にわかるようにかみ砕いて説明するのは存外に難しい。カミュはさらに幼い子どもを相手に小宇宙のなんたるかを説明してみせていたのか、と、今更ながらに亡き同朋の苦労の一端に触れて、頭が下がる思いがする。
「ここに剣があるとする。小宇宙によって力が与えられているわけではない、ただの鉄でできた、だが切れ味は鋭い剣だ。それを握った人間の男が、女神に切りかかったら君はどうする?ちなみに君は聖衣を纏っておらず小宇宙も燃やせないものとする」
「?別に……男を止める。小宇宙を燃やせなくても並大抵の人間には負けない」
「止める暇がないほど不意の出来事ならば?」
「止められずともせめてお嬢さ……女神の盾にくらいはなる」
「その結果、君は大怪我をするかもしれないし、命を落とすかもしれない。聖衣なしの生身ではその可能性も十分にあり得る」
「そうなっても仕方がない。女神を護るのが聖闘士の務めだ。そうだろう?あなただってそうするはずだ」
「いや、俺は違う」
「は?」
「俺たち黄金はそうは動かない。神を害することができるのは同じ神か、その加護を受けた者による攻撃だけだ。人間が作った武器ごときどれほどの威力があろうとも、神を害することはできない。それを知っている以上、必要もないのに無駄にかばって黄金聖闘士が犬死するのはまずい」
「だが、万が一ということがあるじゃないか。あなただってその場にいれば絶対に勝手に身体が動くはずだ」
「まあ、咄嗟に身体が動いてしまう、というのは否定しないが。要は、俺たちは常に女神が『神』であることを忘れていない、という話だ。万が一がないからこそ神だ。神の絶対性を信じている、と言うべきかな」
「だが、絶対なんかこの世にない。万が一うっかり切られるようなことになれば痛いし、身体に傷でも残ったらさすがの沙織さんでも可哀想だ」
女の子の身体に傷跡なんて、と星矢か瞬あたりが嘆くと思う、と氷河が言うのを、だから、神には「万が一」も「うっかり」もないんだ、とミロは苦笑した。
人間であるカミュに対しては『完璧』だと言うくせに、真実、神である女神に対して『万が一』などと案じる氷河はやはりどこかが歪だ。
「君たちの女神に対する認識はずいぶん人間に近いところにあるようだが、本来、聖域では女神は生まれた瞬間から神であり畏怖する存在だ。どんな苦境もそれを使命として生まれたのであって『可哀想』などとは畏れ多くも思えない。女神が俺たちを導くことはあれど、女神を庇護する対象だと思うことはなく、女神を指して『女の子』などと言うこともない」
「……言いたいことはわかるが、だからってそれが何かに影響するとは思えないが」
「いや、大ありだ。青銅の身でありながら臆することなくポセイドンに立ち向かえたのは、我らの神と君たちの距離が近かったことと無関係ではなかった、と俺は思う。本来なら神を相手にすれば……まあ、背を向けて逃げ出していた、とまでは言わんが、深層心理までは普通はコントロールできないからな。対等に戦えるなどという発想はそもそも青銅聖闘士である君たちには起こり得なかっただろうな。神を神として必要以上に畏怖しなかったことで、君たちは奇跡を引き寄せたのかもしれん」
そんなことはないと思うが、と氷河にはやや不服そうだ。
まだ聖闘士になったばかりで、戦闘経験の少ない彼には、自分たちの特異性がまるでわからないのだろう。
「俺達黄金は、神に近づくために、人間らしい感情はできる限り排除して戦うよう訓練されている。だが君たちは……人間として戦うことそのものが強みになっているように思うな。迷いも涙も人間にはつきものだ。君はカミュとまるきり同じにする必要はない。少々泣いたところで折れたりはせん。自分を信じていい」
***
以上、ミロが冗長すぎたな、と思いアナザーディメンションしたシーンでした。
それではまた。